動物福祉について
レアカラーの犬の真実!遺伝リスクと優良ブリーダーの選び方
レアカラーの犬の真実!遺伝リスクと優良ブリーダーの選び方

レアカラーのワンちゃんは、珍しく美しい見た目から注目を集めています。ブルーマールやイザベラなどの毛色は特に人気が高く、一般的な毛色よりも高額で販売されることもあります。
しかし、その希少性の裏には、遺伝疾患や健康リスクの高さといった問題が潜んでいることをご存じでしょうか?
本記事では、レアカラーが生まれる仕組みや、その健康リスク、販売の実態、そしてワンちゃんの健康を第一に考える優良ブリーダーの選び方について詳しく解説します。健康で幸せなワンちゃんを迎えるために、ぜひ最後までご覧ください
レアカラーとは?定義と代表的な毛色

レアカラーとは、犬種ごとに定められたスタンダードカラー(標準の毛色)とは異なる、珍しい毛色のワンちゃんのことを指します。
多くの犬種には、犬種団体(JKC、AKCなど)が定めたスタンダードカラーが存在し、それに基づいて繁殖が行われています。しかし、一部の繁殖者は、「希少で珍しい」というイメージを持たせるために、意図的にレアカラーのワンちゃんを作り出しているのです。
レアカラーの犬は、遺伝的に安定しているとは限らず、見た目の美しさとは裏腹に、健康上のリスクを伴うことがあります。
代表的なレアカラーの例
- ブルーマール(ダックスフンド、ボーダーコリーなど)
- イザベラ(ライラック)(フレンチブルドッグ、ドーベルマンなど)
- パンダカラー(ジャーマンシェパードなど)
- アルビノ(白変種)(シベリアンハスキー、ドーベルマンなど)
レアカラーはどう作られる?遺伝の仕組みと繁殖方法
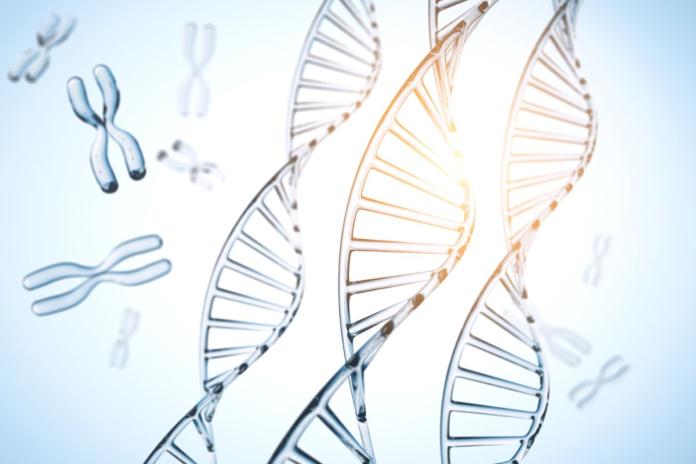
レアカラーのワンちゃんは、偶然生まれるものではなく、特定の遺伝子の影響や繁殖方法によって意図的に作られることがほとんどです。
「珍しい色のワンちゃんがほしい」という需要が高まるにつれて、繁殖者の中には遺伝的な安全性よりも毛色を優先して繁殖を行うケースも増えています。その結果、特定の遺伝子を持つ犬同士を掛け合わせることが一般的ですが、それに伴う健康リスクも懸念されています。
1. レアカラーが生まれる遺伝的要因
レアカラーは、以下のような遺伝子の影響によって発生します。ここでは、どの犬種に見られやすいかも合わせて紹介します。
① マール遺伝子(M遺伝子)
- 影響する毛色:ブルーマール、ダブルマール
- 主な犬種:ボーダーコリー、ダックスフンド、オーストラリアンシェパード、グレートデーン
- 特徴:黒や茶色の毛がまだら模様になる。ダブルマール(両親ともにマール遺伝子を持つ場合)では、毛色が極端に白くなり、視覚・聴覚の異常を伴う可能性が高い。
② 希釈遺伝子(D遺伝子)
- 影響する毛色:イザベラ、ライラック、ブルー(薄いグレー)
- 主な犬種:フレンチブルドッグ、ドーベルマン、ラブラドールレトリバー、ウィペット
- 特徴:通常の毛色が薄くなる。希釈遺伝子が強く影響すると、皮膚疾患が発生しやすくなることがある。
③ パイボールド遺伝子(S遺伝子)
- 影響する毛色:パンダカラー(白黒)、大きな白斑がある毛色
- 主な犬種:ジャーマンシェパード、ダルメシアン、ビーグル、ブルテリア
- 特徴:白色部分が多くなる。色素が不足すると、視覚・聴覚に影響が出ることがある。
④ アルビノ遺伝子(C遺伝子変異)
- 影響する毛色:白変種(アルビノ)、瞳がピンクや青色
- 主な犬種:シベリアンハスキー、ドーベルマン、グレートデーン
- 特徴:完全な色素欠乏により、被毛が白くなる。アルビノの犬は免疫機能が弱く、視覚異常が起こりやすい。
2. レアカラーを出すために行われる繁殖
レアカラーのワンちゃんは、通常の毛色とは異なる遺伝子の影響によって生まれます。中には偶然の遺伝的突然変異によって発生するケースもありますが、ほとんどは意図的な繁殖によって作り出されています。
しかし、これらの繁殖方法には遺伝的な健康リスクや繁殖上の課題が伴うことがあり、慎重な管理が求められます。
ここでは、レアカラーを目的とした代表的な繁殖方法とその課題について解説します。
① 近親交配(インブリーディング)
近親交配とは、血縁関係の近い犬同士を交配させることで、特定の毛色や体型の特徴を固定する方法です。この手法では、目的のレアカラーを高確率で生み出すことができます。
しかし、同じ遺伝子を持つ個体同士の交配を繰り返すと、遺伝的な多様性が失われ、予期せぬ健康リスクが増加する可能性があります。 特に、遺伝性疾患の発症率が高まり、免疫力の低下や繁殖能力の低下が見られるケースもあるため、計画的な血統管理が不可欠です。
② 異種交配(アウトクロッシング)
異種交配とは、通常は交配しない異なる犬種同士を掛け合わせることで、新しい毛色や特徴を生み出す方法です。レアカラーの発現を目的として、特定の毛色を持つ犬種を交配するケースが見られます。
この方法は、近親交配に比べて遺伝的な多様性が確保できるため、健康面でのリスクが若干低くなることがあります。しかし、異なる犬種を掛け合わせることで、体格や骨格のバランスが崩れ、関節の異常や成長不良が起こる可能性もあります。また、遺伝の組み合わせによっては予測しづらい性格や行動特性を持つ場合もあり、しつけが難しくなることもあるため、慎重な交配計画が求められます。
レアカラーの犬が抱える健康リスクとは?

レアカラーのワンちゃんは、遺伝的な健康リスクを伴うことが多いです。
本来、犬の毛色は、長い年月をかけて遺伝的に安定した形で受け継がれてきました。しかし、特定の毛色を求める繁殖が進むことで、遺伝疾患や体質の弱さといった問題が出ることがあります。
ここでは、レアカラーのワンちゃんに見られる代表的な問題を詳しく解説します。
1. 遺伝疾患のリスク
レアカラーを持つ犬は、特定の遺伝子の影響を強く受けるため、通常の毛色の犬に比べて遺伝的な疾患が出やすいことが指摘されています。
① 視覚・聴覚異常(マール遺伝子・パイボールド遺伝子の影響)
- マール遺伝子(特にダブルマール)の影響で、先天的な視覚・聴覚障害を持つ犬が多い
- パイボールド遺伝子(白斑の多い犬)では、色素の欠乏により聴覚異常が発生しやすい
- 片耳または両耳が聞こえないケース、視力が極端に低いケースも
【例:ダブルマールのダックスフンド】
ブルーマールのダックスフンド同士を掛け合わせると、生まれてくる子犬の25%前後が視覚・聴覚に重度の異常を抱えるとされています。
② 皮膚疾患・アレルギー(希釈遺伝子の影響)
- 希釈遺伝子(D遺伝子)を持つ犬は、皮膚が薄く、炎症や乾燥が起こりやすい
- アレルギー性皮膚炎のリスクが高く、慢性的にかゆみや脱毛が見られることがある
- 「イザベラカラー(ライラック)」の犬では、毛が部分的に抜ける「カラー脱毛症」が発生しやすい
③ 免疫機能の低下(近親交配による影響)
- 近親交配が繰り返されると、免疫力が弱くなり、感染症や病気にかかりやすくなる
- ワクチンの効きが弱くなる個体もおり、通常の犬よりも病気の予防が難しくなる
- 傷の治りが遅い、消化器系が弱いなど、健康面での弱さが出ることがある
④ 神経系の異常(特定の遺伝子の影響)
- てんかん発作を起こしやすい個体が多い
- 神経伝達に異常があり、ストレスに弱く、落ち着きがない・パニックになりやすい傾向がある
- 歩行が不安定、筋肉の発達が遅れるケースも報告されている
【 例:ホワイトドーベルマン】
「ホワイトドーベルマン(アルビノ)」は視力や聴覚に異常が出やすいだけでなく、神経系の異常で攻撃性が高まる個体もいるとされています。
2. 診断・治療の難しさ
レアカラーのワンちゃんは、獣医師にとっても診断や治療が難しいケースがあります。
① 症状の現れ方が複雑で誤診されることがある
- 希釈遺伝子を持つ犬は、皮膚疾患とアレルギーの症状が似ているため、診断が難しい
- 聴覚異常がある犬は、行動問題(しつけの難しさ)と混同され、適切な治療が遅れることがある
- 視覚異常を持つ犬は、単なる加齢による視力低下と誤診されることも
② 遺伝的な影響で適切な薬の選定が難しい
- 通常の薬が効きにくかったり、副作用が強く出る個体がいる
- 麻酔のリスクが高い犬が多く、避妊・去勢手術や歯科治療の際にも特別な配慮が必要
③ 成長予測が困難で、適切なケアがしにくい
- 成長後の体格や体質が予測しづらく、適切な食事管理が難しい
- 特定の遺伝子が影響し、骨の成長が遅れる・関節が弱いなどのケースがある
レアカラーの犬が市場で販売される理由

レアカラーのワンちゃんは、スタンダードカラーに比べて珍しく見えるため、「希少価値がある」として高額で取引されることが多く、特にSNSの影響を受けやすい傾向があります。
「他の人とは違う特別なワンちゃんがほしい」という需要が高まるにつれ、市場ではレアカラーの個体が増えていきました。 しかし、その背景には、健康面を考慮せずに繁殖されるケースもあるため、慎重に判断することが求められます。
ここでは、レアカラーのワンちゃんが市場に流通する理由を詳しく解説します。
1. 「希少価値」が強調され、高額で販売される
レアカラーのワンちゃんは、「珍しい」「特別な存在」としてアピールされることが多く、スタンダードカラーよりも高額で販売される傾向があります。
例えば、同じ犬種でもスタンダードカラーの子犬に比べて、レアカラーの個体は2〜3倍以上の価格がつくこともあります。 一部の繁殖業者は、この価格差を利用し、レアカラーの犬を意図的に繁殖して市場に出すことで利益を得ようとします。
特に、ペットショップやオンライン販売では、「限定カラー」「世界に数頭しかいない」といったキャッチコピーが使われ、購入意欲を刺激する販売手法が取られることが多いです。
2. SNSが需要を生み出し、購買意欲を高める
近年、SNSの普及により、「見た目が珍しくてかわいいワンちゃん」が話題になりやすくなっています。
特に、インフルエンサーや有名人がレアカラーのワンちゃんを飼っていると、その犬種や毛色が「トレンド」として広まりやすくなります。SNS上ではフォロワー数の多い著名人が発信する情報が大きな影響力を持ち、「この毛色がかわいい」「おしゃれな犬」として話題になりやすくなります。
また、映画やCMなどのメディアでもレアカラーの犬が登場すると、「同じ毛色の犬を飼いたい」という需要が急激に高まり、繁殖が追いつかないほどのブームを生み出すこともあります。
さらに、レアカラーのワンちゃんは目を引きやすいため、SNS上で拡散されやすい傾向があります。「映える」「特別感がある」といった理由で、多くの人が写真や動画を投稿し、話題になることでさらに需要が高まるという循環が生まれます。
3.一過性の流行が市場を動かす
ペットの世界では、特定の犬種や特徴が流行することで、市場の動きが大きく変わります。レアカラーの人気が高まる背景には、過去に流行した犬種の例と同様に、SNSやメディアの影響を受けた「一過性のブーム」が関係していると考えられます。
例えば、かつて「ティーカッププードル」が話題になった際には、極端に小さいサイズの個体が求められ、健康面を考慮しない繁殖が行われた結果、低血糖症や骨のもろさ、内臓疾患を抱える犬が増えました。
このように、ペット市場は流行に大きく影響を受けやすく、「珍しい毛色が売れる」という状況が生まれると、それを目的とした繁殖が加速し、結果的に健康管理が後回しにされることがあります。
レアカラーの犬も同様に、毛色の希少性が強調されることで、無理な繁殖が横行するリスクがあります。
優良ブリーダーは健康を優先する|スタンダード繁殖の重要性

優良ブリーダーは、犬の健康と福祉を最優先に考えた繁殖を行います。 そのため、レアカラーの犬が市場で注目されていても、健康リスクを伴う可能性のある繁殖には慎重な姿勢を取ります。
ここでは、優良ブリーダーがどのような繁殖方針を持ち、どの点に配慮しているのかを解説します。
1.犬種のスタンダードに沿った繁殖を行う
犬種ごとに定められたスタンダード(理想的な体格や毛色、性格などの基準)には、長年の歴史の中で培われた「その犬種が健康に生きるためのバランス」が考慮されています。
- レアカラーは、犬種標準に含まれないことが多く、健康面での十分な研究がされていないケースがある
- 犬種本来の体質や気質を維持するために、標準カラーの犬を優先的に繁殖する
- 血統がしっかり管理され、長期的に安定した繁殖計画ができる
レアカラーを求める声があるとしても、優良ブリーダーは健康を第一に考え、遺伝的な安定性を確保することを優先します。
2.健康リスクが高い組み合わせを避ける
レアカラーの犬は、特定の遺伝子の影響を強く受けるため、遺伝疾患や健康上の問題が発生するリスクがあることが分かっています。
- ダブルマールなど、視覚・聴覚異常のリスクが高まる交配は行わない
- 近親交配を避け、遺伝病の発生リスクを最小限に抑える
- 毛色を優先するために、健康状態の悪い親犬を繁殖に使わない
優良ブリーダーは、毛色の希少性よりも、遺伝的に健全な犬を育てることに重点を置いています。
3.市場の流行に流されず、計画的な繁殖を行う
レアカラーの犬は、高額で取引されることが多いため、「売れるから」という理由で繁殖を行う業者も少なくありません。しかし、優良ブリーダーは流行に左右されることなく、長期的な視点で繁殖を計画します。
- 「希少だから価値がある」のではなく、「健康で長く幸せに暮らせること」が最も重要と考える
- 短期間でブームになった犬種や毛色は、無計画に繁殖されやすいため、慎重に判断する
- 一過性の流行によって大量に繁殖・販売され、その後飼育放棄されるリスクを考慮する
その犬が一生を健康に過ごせるかどうかを考えた上で、繁殖の判断をするのが、優良ブリーダーの姿勢です。
健康なワンちゃんを迎えるために知っておきたいこと

ワンちゃんを迎える際には、「珍しい=品質が良い」というわけではないことを理解し、見た目の珍しさではなく、健康や性格を重視することが大切です。
毛色にこだわりすぎると、健康面のリスクを見落としてしまう可能性があり、結果としてワンちゃんが長く健康に暮らせない原因になることもあります。
ここでは、健康なワンちゃんを迎えるために大切なポイントを解説します。
1.見た目ではなく、健康と性格を重視する
犬を迎える際、多くの人が「かわいい」「珍しい色だから特別」といった見た目の要素に惹かれがちですが、ワンちゃんと長く幸せに暮らすためには、健康と性格のほうがずっと重要です。
✅ 健康を優先する理由
- レアカラーの犬は、遺伝疾患や視覚・聴覚の異常、皮膚トラブルなどのリスクを持つことがあるため、健康状態の確認が不可欠
- 短期間の流行や市場の需要によって無理な繁殖が行われた個体は、健康管理が不十分なケースがある
- 一緒に暮らす中で、頻繁に動物病院に通うことになったり、治療費がかかるリスクが高まる
✅ 性格も重視すべき理由
- ワンちゃんは見た目だけでなく、性格が飼い主のライフスタイルに合っているかが重要
- レアカラーにこだわるあまり、性格面の適性を見落とすと、しつけが難しくなったり、ストレスを抱えやすい状況になりやすい
- 「かわいい」だけでなく、家族として迎えられる子かどうかを慎重に考えることが大切
2.信頼できるブリーダーを選ぶ
健康なワンちゃんを迎えるためには、信頼できるブリーダーを選ぶことが最も重要なポイントのひとつです。
見た目の珍しさや価格ではなく、ワンちゃんの健康と幸せを考えて繁殖しているブリーダーを選ぶことが大切です。
✅ 優良ブリーダーの見極めポイント(例)
- レアカラーや極端な小ささなどの見た目よりも、健康を最優先に考えて繁殖を行っている
- 少数の純犬種にしぼり、犬種ごとの特性や健康管理を徹底している(ミックス犬の繁殖は行わない)
- ペットショップやペットオークションを使わず、直接の飼い主との対話を大切にしている
- 健康管理や食事、運動、衛生面にしっかり配慮している
- 社会化を重視し、子犬が人や環境に慣れるよう適切な育て方をしている
- 親犬や飼育環境の見学が可能で、誠実に情報を公開している
BreederFamiliesでは、18の基準を定めて、優良ブリーダーのみを厳選して紹介しています。
✅ 避けるべきブリーダーの特徴
- 「この色は珍しいから高額になる」「今しか手に入らない」と煽るような販売をする
- 健康状態や親犬の情報を十分に公開せず、「大丈夫」と曖昧に説明する
- 見学を断る、または見せる部分を制限する
まとめ
レアカラーのワンちゃんは、確かに見た目が魅力的ですが、遺伝疾患や健康リスクの高さを理解した上で慎重に選ぶことが重要です。
特に、健康を考えずにレアカラーを目的に繁殖されるケースでは、視覚・聴覚異常や皮膚疾患、免疫低下などの問題が発生しやすくなります。
健康なワンちゃんを迎えるためには、見た目の珍しさではなく、健康や性格を重視すること、信頼できるブリーダーを選ぶことが大切です。BreederFamiliesでは、健康管理や犬種の適正な繁殖を重視するブリーダーのみを厳選して紹介しています。
ワンちゃんの一生を考えた最良の選択をするために、レアカラーの魅力だけでなく、健康や飼育環境にも注目しましょう。
Breeder Familiesについて

BreederFamiliesのブリーダーを通じて ワンちゃんをお迎えすることが、 ペットをとりまく社会課題の解決に繋がります。
私たちが目指すのは、営利優先の悪徳ブリーダーを減らし、責任と愛情を持つ優良ブリーダーを支援することで、ワンちゃんの福祉が守られる社会の実現。
目の前の子犬だけでなく、親犬や引退犬も大切にされる環境を作り上げ、すべてのワンちゃんに優しいブリーディング環境の普及にむけて活動しています。









