ブリーダー評価基準
優良ブリーダーの見分け方⑥_引退犬も大切に
優良ブリーダーの見分け方⑥_引退犬も大切に

ワンちゃんの繁殖を終えた「引退犬」が、ブリーダーからどのように扱われるかは、そのブリーダーが本当にワンちゃんを「家族の一員」として大切にしているかを判断する重要なポイントです。引退犬がその後も幸せな生活を送るためには、繁殖期後もきちんとしたケアや適切な環境が整っている必要があります。本記事では、引退犬を家族のように大切に扱う優良ブリーダーの特徴と、その理由について詳しく解説します。また、営利優先ブリーダーが引退犬をどのように扱うか、その問題点も明らかにし、ワンちゃんをお迎えする際に信頼できるブリーダーの見極め方についてもご紹介します。
引退犬とは
引退犬とは、繁殖期を終えたワンちゃんたちを指します。一般的に、法令では最大7歳まで出産可能ですが、個体差や健康状態により引退年齢は異なります。繁殖の役割を終えたワンちゃんたちは、それぞれの体力や健康を維持するために、適切な環境と生活の変化が必要です。繁殖期にブリーダーと共に生活を支えてきた引退犬にとって、引退後も安定した生活環境が保障されるかどうかは、ブリーダー選びにおいても見逃せないポイントです。
引退犬を大切にする優良ブリーダーの特徴
1. 引退犬も家族と考えている

優良ブリーダーは、引退犬を単なる「繁殖用の動物」として扱うのではなく、繁殖を通じて共に過ごした「家族」として見ています。そのため、引退犬の扱いにも特別な配慮が見られ、以下のような特徴が見受けられます。
- 一緒に頑張ってきた家族として深い愛情を持っている:引退犬は繁殖期を通じてブリーダーの生活の一部であり、パートナーとしての役割を果たしてきました。よって、優良ブリーダーは、この長い間ともに過ごしてきた絆を重視し、引退後も幸せになって欲しいと考えています。
- 費用がかかるからといって簡単には手放さない:引退犬のケアには医療費や生活費などがかかりますが、優良ブリーダーはそれを理由に、ワンちゃんを簡単に手放すことはしません。これは、ワンちゃんを経済的な「コスト」ではなく、愛する家族と見なす姿勢の表れです。
- ワンちゃんの幸福を第一に考え、最適な選択をする:優良ブリーダーは、ワンちゃんが終生幸せに過ごせる環境を考慮し、引退後も幸せに暮らせる方法を模索します。終生飼育が理想的と判断すれば自ら飼育を続けますが、信頼できる新しい飼い主を見つけた場合には、その選択も慎重に検討します。
2. 選択肢①:最後まで自分のペットとして飼育する
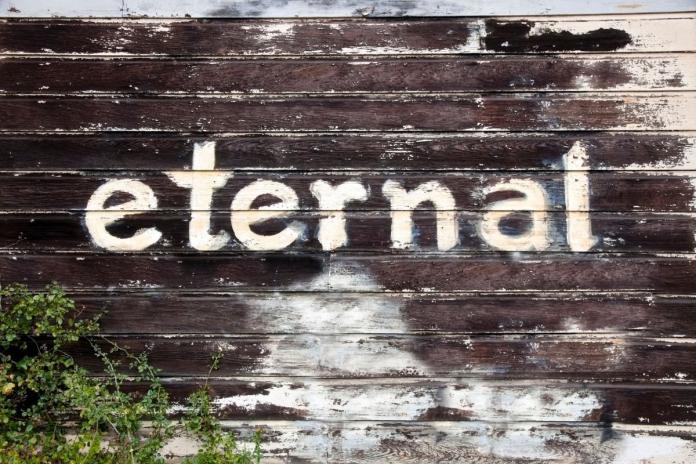
優良ブリーダーは、引退犬を最後まで自分のペットとして共に暮らす責任を強く感じています。繁殖期間中に共に過ごしてきたワンちゃんに対する愛情と感謝から、引退後も一緒に生活することを選びます。この場合、ブリーダーは引退犬に適切な医療サポートや生活環境を整え、安心して老後を過ごせるよう尽力します。
引退後も定期的な健康管理や医療ケアを継続し、ワンちゃんができる限り快適に暮らせるよう配慮するのが特徴です。
3. 選択肢②:誰かに譲る場合は、信頼できる相手にのみ譲る
引退犬をすべて終生飼育するのが難しい場合、優良ブリーダーは信頼できる新しい飼い主に引退犬を譲ります。しかし、この際にも細心の注意が払われます。
- 新しい飼い主に譲る際には厳選:ワンちゃんの新しい生活環境が十分に整っているかどうか、愛情をもって育ててもらえるかなどを考慮し、信頼できる飼い主候補を慎重に選定します。譲渡先としては、ワンちゃんの過去の飼い主や友人、信頼できる知人が譲渡先の候補となる場合が多く、顔を見て話せる人に限定することで、ワンちゃんの新生活の安定性を確保します。
- 一般家庭での生活に適応できるよう、健康管理や社会化も考慮:新しい家庭にスムーズに馴染むため、引退犬にも一般家庭での生活に必要な健康管理や社会化、基本的なしつけが行われています。これにより、引退後も快適で安定した生活が送れるようサポートしています。
引退犬を大切にしない営利優先ブリーダーの特徴
1. 引退犬をコストとして考えている

営利優先ブリーダーは、引退犬を単なる「コスト」として扱い、引退後の世話には関心が薄い傾向があります。引退犬にかかる費用を負担したくないため、できるだけ早く手放すことを考えるため、ワンちゃんの将来を考えない行動が見られます。
2. 悪徳保護団体とつながっている引き取り屋に渡してしまう

営利優先ブリーダーは、引退犬を「不要なコスト」として扱い、無料で引き取ってくれる業者に引き渡すことがあります。しかし、こうした業者の中には悪徳保護団体とつながり、以下のような社会問題を引き起こすケースもあります。
- 本来保護犬でない引退犬が「保護犬」として高額譲渡される:引退犬が保護犬として扱われ、本来の保護犬ではないにもかかわらず、高額な譲渡金が設定されることがあります。その場合、寄付金として処理されることもあり、これが社会的な問題として注目されています。
- 譲渡要件の緩さと再譲渡のリスク:譲渡の要件が緩いため、譲られた先でまた手放され、再び保護団体に戻ることもあります。このようなケースでは、ワンちゃんが安定した生活環境を得られず、何度も引き渡されるストレスを抱えることになります。
3. 譲渡を前提とした健康管理や社会化、しつけを行っていない
営利優先ブリーダーは、引退犬の一般家庭への適応を考慮せずに、健康管理や社会化のためのしつけを行わないまま手放すことが多く、以下の問題が発生しやすいです。
- 健康に配慮せず法令上限まで繁殖させている:健康を考慮せず、法令の上限まで繁殖させた結果、体力が衰えた状態で引退するケースがあり、これが引退犬の健康問題の原因となります。
- 社会化が不足している:引退犬は、繁殖用として生活してきたため、他の犬や人間との社会化が不足しており、新しい家庭に引き取られた際にトラブルが生じることがあります。
- 基本的なしつけが施されていない:引退犬は繁殖用として飼育されてきたため、一般家庭で必要なしつけがなされていないことが多く、トイレの場所や基本的な生活ルールが身についていないため、適応に困難をきたすケースもあります。
まとめ
引退犬をどのように扱うかは、そのブリーダーがワンちゃんを「家族」として見ているかどうかを判断する大きなポイントです。ワンちゃんを家族のように大切にする優良ブリーダーは、引退犬にも愛情と責任を持ち、終生ケアや安心できる譲渡先の確保を重要視します。
一方で、営利優先ブリーダーは引退犬をコストとして扱い、無責任な譲渡が社会問題を引き起こすこともあります。
BreederFamiliesでは、このような引退犬への配慮も評価基準に含め、安心してワンちゃんをお迎えできる優良ブリーダーのみを紹介しています。
Breeder Familiesについて

BreederFamiliesのブリーダーを通じて ワンちゃんをお迎えすることが、 ペットをとりまく社会課題の解決に繋がります。
私たちが目指すのは、営利優先の悪徳ブリーダーを減らし、責任と愛情を持つ優良ブリーダーを支援することで、ワンちゃんの福祉が守られる社会の実現。
目の前の子犬だけでなく、親犬や引退犬も大切にされる環境を作り上げ、すべてのワンちゃんに優しいブリーディング環境の普及にむけて活動しています。









